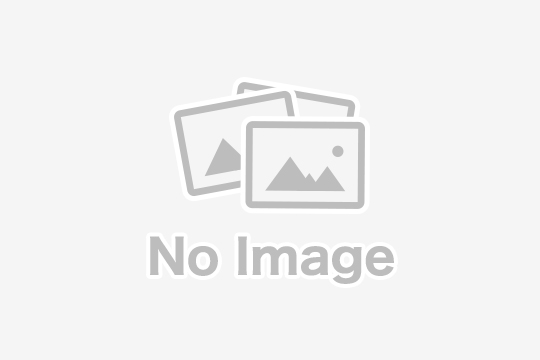MO
発声練習
指摘したことは、ブレス時に瞬間的に腹筋に力を込めること。
声を出し始める状態にプラスに働くからである。
トスティのソルフェッヂから2番
まず声はピアノのヘ音記号の音が実音である、という前回指摘したことを思い出してもらった。
これは彼の場合特に大事なことなので、忘れないように。
発声練習のときから実現できるように。
レガートに歌うことについて練習。
この場合は、特に音程が跳躍するフレーズの場合である。
ラララでも母音でも同じだが、拍に乗り過ぎると音の出が遅くなる傾向になる。
これは跳躍という発声上の課題もあるだろう。
声を共鳴させるように口を開けることで、倍音が感じられるはず。
その倍音に乗ってメロディを歌おうとすることで、息の流れで歌う感覚になる。
それが出来ればレガートは自然に達成される。
つまり音そのもので時間を追う限りは、必ず音の出は遅れるのである。
声の響きが息の流れで歌えていれば、自ずと拍節に依存せずに自然なリズム感を産み出せるのである。
イタリア古典歌曲集からTu lo sai
TuのU母音での中高音発声の場合、下あごを降ろしてO母音のようにすることで喉を締めずに対処できる。
前回練習したこの方法による感覚を、彼は良くつかんだようで、この曲の高音発声は無理なく対処できるようになっていた。
つまり喉を上げるとどういう声になるか?という体感が会得出来れば、そのようにならない方法を自ずと見つけられるのである。
トスティ「もう君なんか・・」
高音発声が課題。
今回は歌わないで朗読をすることで、喉の対処を覚えてもらった。
文章にするのは難しいのだが、一言で言えば喉を上げずに高いトーンで語るということ。
つまり地声の低い声で朗読してはいけないということ。
私が手本を見せて真似してもらった。
まだ息漏れが出る声だが、喉を高くしないで歌うきっかけはつかめていると思われた。
あとは回を重ねて慣れることである。
信時潔 歌曲集「沙羅」より「丹澤」
テンポが全体に前のめり気味。
ゆったりしたリラックスした気分を大切に。
また楽譜に指示がある、更にゆっくりと歌う箇所を尊重してほしい。
声の課題は高音である。
あるいは中高音への跳躍するフレーズの処理。
滑らかに声が締まらないようにレガートに歌う方法については前述の通りである。